大学の大先輩・梶光一東京農工大学名誉教授の著書『ワイルドライフマネジメント』を読んで:その1
2025年8月7日
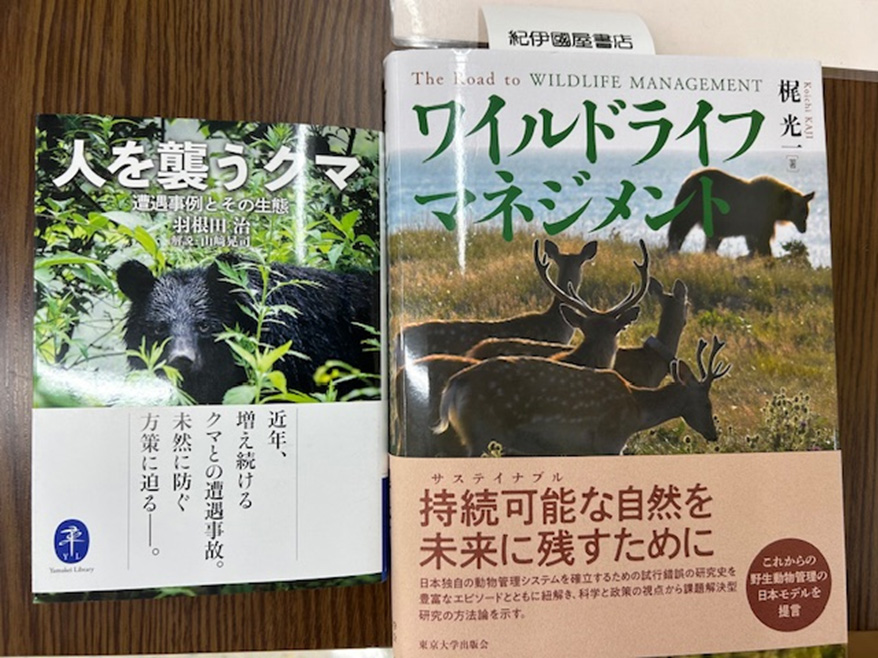
今年(2025年)春の盛岡滞在時ですが、4月2日に盛岡駅近くで熊出没騒ぎがあり、別の日には、鹿の罠が掛けられるところを徘徊している熊とそれを貪り食う画像がテレビで放映されるなど野生動物と人間の関わり方が気になっていました。野生動物と言えば、個人的にはどうしても絶滅種や危惧性が気になりニホンカワウソやアマミノクロウサギなどが頭に浮かんでくるのですが、昨今は大型獣(シカ・イノシシ・クマ類)の生育数が日本では急激に増加しており、その分布域も拡大しているのだと気づきつつありました。また、ケニアの国立公園の一つであるアンボセリ(キリマンジャロの麓)ではアフリカゾウが増加して園内の植物だけでは生息できなくなってきていることや、ネパール・インドでは野良ゾウが住民の畑を荒らして迷惑だといった話も思い出したのです。

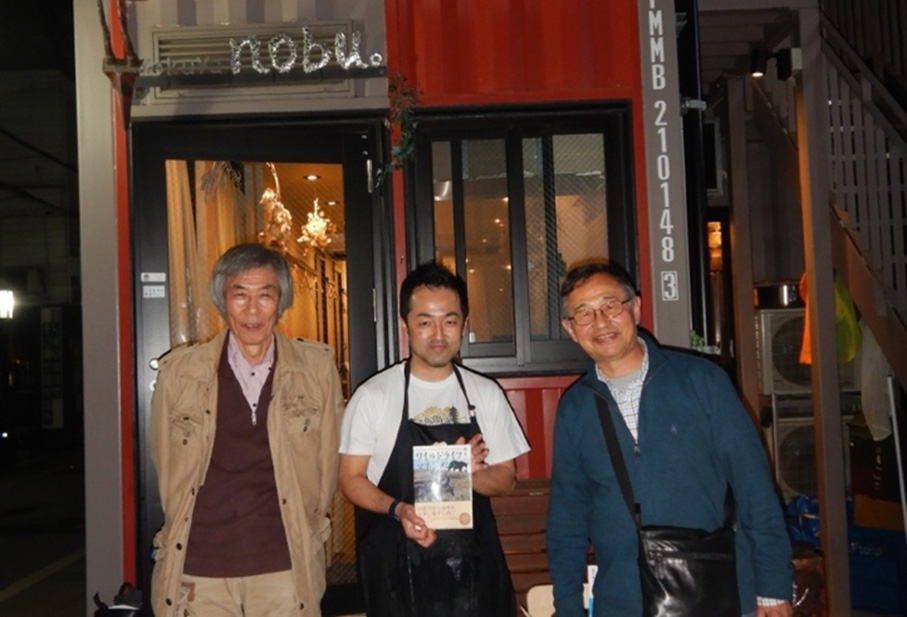
晩餐の場では、うろ覚えながら、北海道の鹿肉は100年以上前にはヨーロッパに堂々と輸出されており肉質も味も申し分ないこと(つまりEU向けに輸出できて稼げる商品)とか、ヨーロッパの大学、特にドイツとかは学部できちんと狩猟学を学び、ライフルを実践で使えるように訓練されている(スウェーデンも然り)といったことが話題になっており、もうちょっと詳しく知りたいなあと少し二日酔いの頭で翌朝思ったものです。
梶さんの近著は『ワイルドライフマネジメント』とあえて和訳していないタイトル。野生動物管理とでも訳せそうですが、東京大学出版会から既刊で『野生動物管理システム』を出版している(こちら未だ読んでいません)から敢えてこういうタイトルにしたのかもしれません。1冊4200円は高いなあと思いつつも、講演料かな?と思って新宿の紀伊國屋で早速買うことにしました。
- 2025年3月28日(金)於:新宿区榎町地域センター 4F多目的ホール
日本の鹿研究の第一人者である梶光一さん。野生動物と今後どう共存していくべきかを語っていただきます。「日本では年間60万頭の鹿を獲っているけど、それでも増え続けています。せっかくの肉や毛皮は利用もされず、ほとんどが捨てられてる」というのは日本の鹿研究者の草分け、第一人者、梶光一さん(71)。縄文の昔から野生動物を“畏れ敬いながら利用”してきた日本の技術や文化が途絶えたのはこの一世紀ほど。この間に、鹿、猪、熊などは著しく増えました。「農林業や環境への影響だけじゃなくて、最近はヒトとの接触事故も。でも未だに野生動物とうまく共存する方法論がないのが日本の現状です」。東京の下町出身。北海道大学農学部林学科の学生時代にヒグマを論文テーマに設定。森林管理に野性動物対応の概念が抜けていた当時の日本林学界では異端児でした。当時増えはじめていたエゾシカを対象に変更し、頭数を把握する試みから四苦八苦の手探りをはじめます。「環境適応力も繁殖能力もハンパない日本の鹿と共存するには、獲って食べる仕組みを本器で考えないと」。今月は梶さんに、シカをはじめ、これから我々は野性動物とどうつきあっていけばいいのか、その考え方を語って頂きます!
(続く)
参考文献:
梶 光一(2025a) 平成林業逸史(61)「野生動物管理と森林管理」山林 1691:10-16 大日本山林会
梶 光一(2025b)特集 野生動物と人間 第一部 野生動物と人間をめぐる関係を見るための視座 学問と実践をつなぐ 野生動物管理学の役割 『森林環境2025』
42-50 森林文化協会 https://www.shinrinbunka.com/publish/shinrin/
梶 光一(2025c)特集 日本人が森に学ぶこと 野生動物管理 ヒトと野生動物はどのように共存するのか 神籬 71:3-8
(オランダ通信 2025年4月号 2025月5月2日発行から)

